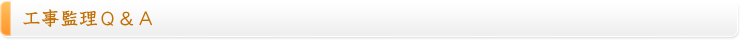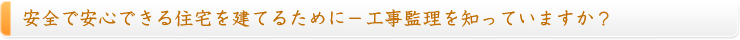
近年、施行不良などが原因で生じる欠陥住宅に関するトラブルが、大きな社会問題となっています。せっかく苦労して手に入れた、人生の中でもっとも大きな買い物であるマイホームに重大な欠陥があっては大変です。そこで、マイホームの工事全体について、建築士の資格を持った専門家がきちんとチェックすること、すなわち「工事監理」が重要になっています。
住まいづくりでは、建築主が建築士である工事監理者を定めなければならないことになっています。しかしながら、これまでは適切な工事監理が行われないことがありました。工事監理が適切に行われていれば防ぐことができた欠陥住宅などの被害がたくさんあったはずです。今、豊富な専門知識と経験を持つ工事監理者の役割が、ますます重要になっています。
建築物の設計や工事監理を行う建築士の資格を定め、その業務の適正化と、建築物の質の向上を図ることを目的としています。建築物の用途、構造、高さに応じて、一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければ、設計、工事監理を行ってはならないこととされています。
建築物を建てる場合に必ず守らなければならない法律です。地震や火災などに対する安全性や、敷地、周囲の環境などに関する基準など、建築物が満たすべき一定の性能を定めています。
住宅の品質を確保して、住宅購入者の利益を保護します。また、住宅に関する紛争をすみやかに解決して、住宅購入者の生活を守ります。
・瑕疵担保責任の特例制度(すべての新築住宅に10年間義務化)
・住宅性能表示制度(任意)
住まいづくりにおいては、建築主・設計者・工事監理者・施工者・行政などの連携プレーが大切です。なかでも、工事監理者は、建築主の代理人として設計図書どおりに施行が行われているかを確認し、欠陥の発生を未然に防ぐとともに、関連業務として施工者選びのアドバイスや工事代金に関するチェックを行うなどの重要な役割を担います。
「工事監理業務委託契約」を結んで、依頼する工事監理業務の内容を明らかにしておきましょう。設計と施工を一括で契約する場合でも、工事監理の契約を別途結ぶことができます。また、工事監理だけを第三者に依頼することが可能です。工事監理は登録を受けた建築士事務所の建築士が行います。
住まいづくりの工程は、とても複雑で広範囲です。しかし、適切な工事監理が行われれば、後々大きな補修が必要となるような致命的な欠陥を防ぐことができるはずです。ですから、どの工程の項目をどのような方法で確認するかが重要になってきます。工事監理者と十分に相談して工事監理の内容を決めましょう。
※数ある施工工程の中から、工事監理の確認内容についてのポイントをまとめた「重要な工事監理のポイント例」をご参照下さい。
住まいづくりに関する建築主の決定事項は、業者(設計者、工事監理者、施工者)の選定・契約に始まり、間取りや費用などのとても重要なことから、ドアノブやスイッチの位置などの細かなことまで数多くあります。しかし、これらの決定が業者に対する無理な要求であったり、反対に業者に任せきりの状況のものであっては、住まいづくりを成功させることは困難です。住まいづくりに関する決定は、建築主が自ら、責任を持って行いましょう。
工事監理や施工は設計図書に基づいて行われるので、設計と書には住まいづくりに必要な情報が書かれていなければいけません。ですから、設計図書の作成は信頼できる建築士に依頼し、できるだけ詳細な部分まで具体化しておきましょう。
施工者は、設計図書どおりの住宅を工事請負契約書に定められた工期と金額で建てなければなりません。そのために、施工管理者としての現場監督を中心に施工の品質、工程の進捗状況、専門業者等の管理を行います。
設計図書の段階で「建築確認」、工事の段階で「中間検査」と「完了検査」が行われます。
※対象となる建築物や検査工程は建築地の特定行政庁(都道府県または市区町)が指定しています。
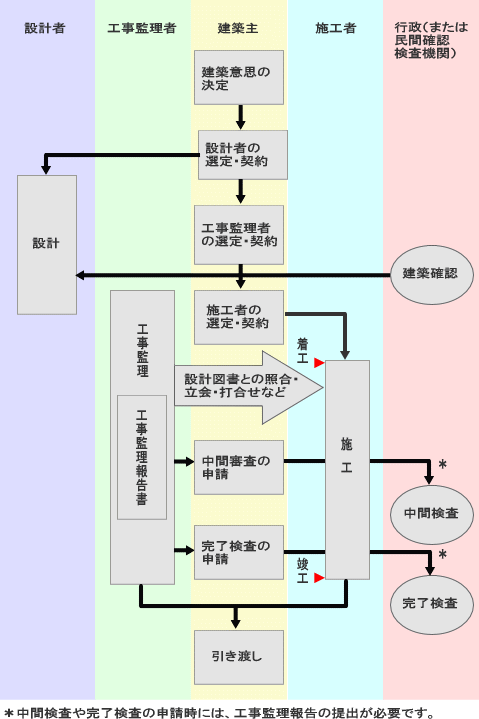
この図は、建築主と工事監理者、施工者の間で工事監理業務に関してどのようなことが行われるかを順を追って説明したものの一例です。(在来工法の木造戸建て住宅の場合)
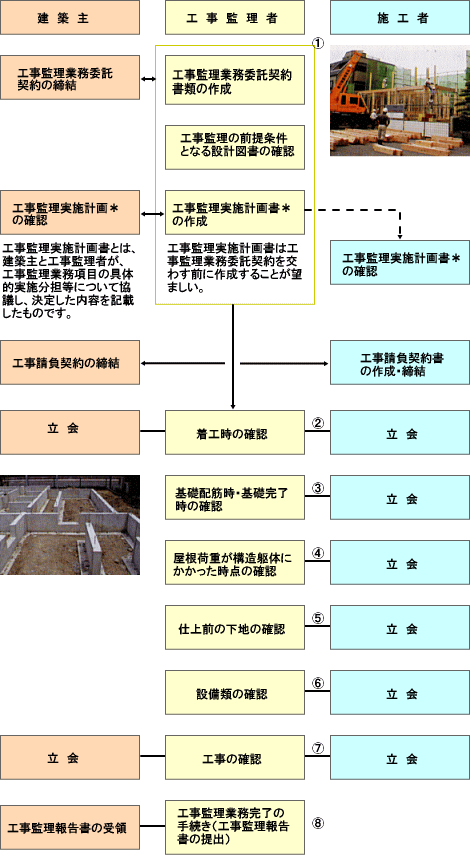
重要な工事監理のポイント〔例〕 この例は在来工法の木造戸建て
この例は在来工法の木造戸建て住宅について、設計図書に通常記載されている内容を前提として、数ある施工工程の中から特に重要な工事監理のポイントをまとめたものです。
表示:▲・・・特約業務 ●・・・建築主の立会、確認が望ましい項目
| 確認の時期と内容 | 備考 | 確認の時期と内容 | 備考 |
| 工事期間全般 | 4[屋根荷重が構造躯体にかかった時点の確認 (続き)] |
||
| ◆設計意図を施工者に正確に伝えるための業務等 | ◆筋かい等 | ||
| ・施工者との打ち合わせおよび協議 | ・配置、品質・樹種・形状・寸法の確認 | ||
| 1 着工前 | ・構造耐力上支障のある断面欠損の有無の確認 | ||
| ◆建築主との工事監理実施計画の協議等 | ・代替工法(構造用合板等)の場合の確認 (特に設計図書に記載がある場合) |
||
| ・工事監理実施計画の協議 | ● | ◆接合方法(継手・仕口) | |
| ・工事監理実施計画書の作成 | ● | ・接合部、継手・仕口の確認 | |
| ◆設計意図の把握等のための業務 | ◆使用接合金物 | ||
| ・設計図書の確認 | ・使用接合金物の確認 | ||
| ・設計図書の内容の精査 | ▲ | ◆構造用木材の含水率 | |
| 2 着工時の確認 | ・構造用木材の含水率の確認 (特に設計図書に記載がある場合) |
||
| ◆着工時の敷地、建物位置および高さ | ◆建物の高さの再確認 | ||
| ・敷地形状、境界の確認 | ● | ・道路斜線・隣地斜線・北側斜線の照合 | |
| ・方位の確認 | 5 仕上げ前の下地の確認 | ||
| ・建築物の敷地内の位置の確認 | ● | ◆軒裏、外壁 | |
| ・前面道路中心線からの地盤面の高さの確認 | ・防火上の措置の確認 | ||
| ◆地耐力 | ◆壁体内結露防止対策 | ||
| ・データの出所の確認 (設計図書に地盤調査書が添付されていない場合) |
・壁体内結露防止対策の確認 | ||
| ・設計地耐力と実際の地耐力の確認 | ▲ | ◆屋根(バルコニー)・外壁・防水・開口部・シーリング状況 | |
| ・試掘 | ▲ | ・屋根(バルコニー)下地材料・形状の確認 | |
| 3 基礎配筋時・基礎完了時の確認 | ・外壁・防水・開口部・シーリング状況の確認 | ||
| ◆地業 | ◆軸組の防腐・防蟻処理 | ||
| ・地業、形状、寸法、配置の確認 (特に設計図書に記載がある場合) |
・軸組の防腐・防蟻処理の確認 | ||
| ◆基礎配筋 | 6 設備類の確認 | ||
| ・基礎形状、寸法、配置の確認 | ◆設備類 | ||
| ・基礎配筋、床下換気口周り等の補強の確認 | ・排水管の排水状況の確認 | ||
| ・鉄筋・アンカーボルトの材質の確認 | ・排気管の排気状況の確認 (室内の煙突工事を伴う場合) |
||
| ・アンカーボルトの位置・本数の確認 | 7 工事完了の確認 | ||
| ◆床下換気と床下防湿 | ◆開口部 | ||
| ・床下換気口又はこれに代わるものの確認 | ・防火設備の種類の確認 | ||
| ・床下防湿方法の確認 | ◆シーリング状況 | ||
| 4 屋根荷重が構造躯体にかかった時点の確認 | ・シーリング状況の確認 | ||
| ◆土台 | ◆設計内容の最終確認 | ||
| ・アンカーボルトの緊結および継手等の確認 | ・設計図書との照合 | ||
| ・土台の品質・樹種・形状・寸法の確認 | ◆不具合工事の有無 | ||
| ・防腐・防蟻処理の確認 | ・不具合工事の有無の確認 | ● | |
| ◆耐力壁の壁量 | ◆官公庁等の検査 | ||
| ・耐力壁の位置・長さ・規格の確認 | ・官公庁等の検査の立会い | ||
| ◆構造材(柱・横架材、小屋組等) | 8 工事監理業務完了手続き | ||
| ・品質・樹種・形状・寸法の確認 | ◆工事監理業務完了の手続 | ||
| ・構造耐力上支障のある断面欠損の有無の確認 | ・工事請負契約の目的物の引渡し立会い | ● | |
| ・工事監理報告書等の提出 |