
HOME > 一般の皆様へ > マイホーム新築のチェックポイント

工事に関するトラブルを防止するためには、建築主も工事の発注者としての自主性と責任を十分に自覚することが必要です。(トラブルの例)
・設計や施工が考えていたものと違う。
・手直し工事を満足にやってくれない。
・追加工事の費用が高すぎる。等
そこで、特に着工するまでの間に、建築主が「心得ておかなければならないこと」や「しなければならないこと」を、次のようにまとめました。
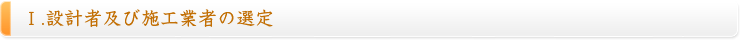
設計とは、建築主が希望する具体的な内容や工事の方法などを図面や文章で表現することです。これを行う者を「設計者」といいます。
(例)建築士事務所が最近設計した住宅や施工業者が最近建築した住宅を実際に見る。さらに、建築主に直接話を聞く。 (例)設計者又は施工業者の選定にあたって、信用度、会社の規模や請負工事量などにも十分気を配って選定する。
設計者及び施工業者との打合せが不十分であったために、自分が思っていた通りの住宅にならなかったり、工事途中で仕様の変更を行ったために追加工事が発生することがあります。自分の住まいのイメージや希望、注文をお互いが納得のいくまで打ち合わせをしたうえで、設計者や施工業者を決定しましょう。
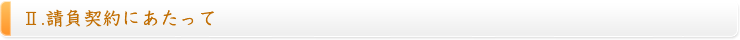
(例)建築主の意向を反映した設計図書に基づき、複数の施工業者から工事費を見積もってもらい、設計を頼んだ建築士に見積書の内容をチェックしてもらう。
文書によらず口約束だけで工事をまかせるのは、トラブルの原因となり大変危険です。
請負契約が設計図書が添付されていないと、どのような住宅を注文したのか不明確になります。契約上の条件がはっきりせず、いざというときに困ることになります。 (例)第三者に損害を与えた場合、工事中の火災保険、瑕疵(かし、欠陥のこと。)の負担。
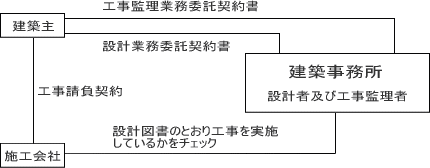
請負契約について、次の点からチェックしてください。もし抜けている点があったら施工業者に確認しましょう。
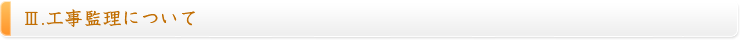
工事監理とは、設計図書(図面、仕様書等)どおりに施工されているか否かを工事中の現場に赴き、「建築主の立場」に立って確認を行うことです。
工事監理をするためには、建築に関する豊富な知識と経験が必要です。現場では、設計段階では予測できなかったことが発生し、設計どおり施工できない事態が生じた場合、設計に示された建物の諸性能を損なわないように方法を講じて施工業者に指示しなければなりません。 法律では、100㎡以下(木造2階建)の建物は工事監理がいらないが、トラブルの多いのも・・・。
専門的なことは工事監理者にまかせるにしても、建築主はその建築現場の当事者として、時々現場をみて施工状況を把握して理解する必要があります。 また、特に重要と思われる施工上のポイントについて、施工業者側の工事責任者の説明を受けることをお勧めします。