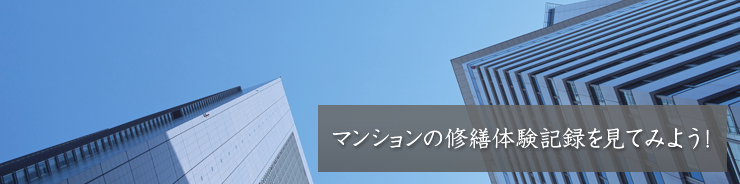
HOME > 一般の皆様へ > マンションの修繕体験記録を見てみよう! > 過去3回の大規模修繕をふりかえって
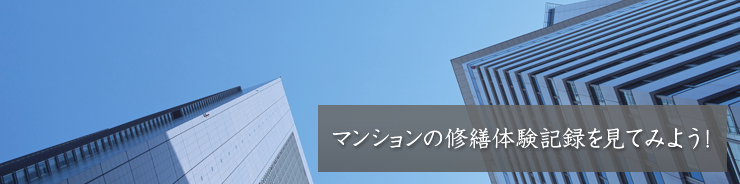

| 建物 | 鉄筋コンクリートプレハブ構造5階建て 外壁;塗装仕上、エレベーターなし |
| 住戸数 | 310戸(10戸棟14棟、20戸棟7棟、30戸棟1棟) |
| 管理形式 | 自主管理形態 一部管理委託 |
| 修繕履歴及び計画 | |
| 第1回大規模修繕 | 築後11年(昭和58年) |
| 第2回大規模修繕 | 築後18年(平成 2年) 築後28年 20年計画作成(管理会社委託、組合修正) |
| 第3回大規模修繕 | 築後29年(平成13年) |
| 第4回 予定 | 築後42年(平成25年) |
上表は大規模修繕の概要で周期は約10年、今後は12年を目指しています。
修繕積立金は大規模修繕Aと計画修繕Bに使われます。Aは足場が必要な工事をここで集中的に行いますが、Bは計画のもとに必要に応じて行う工事で大型の工事が含まれます。
A,Bとも長期計画として5~6年毎に見直し、状況を見ながら工事期を早めたり、遅らせたりして調整します。
300~400戸前後の組合でも建築専門家は少なく、2回、3回と同じ居住者が修繕委員の核になることも珍しくないようです。過去の施工状況を把握しながら仕様計画を練るのはメリットであり、大きな経費削減に繋がります。居住者自身の参画は住民全体の状況を把握しながら、特に資金計画に厳しく事業遂行し、大きな役割を果たします。専従に近い状態になることもあります。
「修繕計画の作成には建物・設備、資金運用にも専門的知識が必要なので、管理会社や設計事務所へ頼むケースが多くなっている。ただし、計画主体は管理組合であり、組合の意見や要望が反映された計画とすべき(マンション管理の知識)」と謳われています。
分譲から11年後の1983年5月区分所有法改正に至るまで管理会社の全部委託管理のため、組合はなく自治会が全体をまとめる組織でした。しかし、第1回大規模修繕は結果として自治会組織よる修繕計画の策定と自治会直接発注工事なりました。その時の修繕委員は12人、自治会長はじめ建築専門委員3名が加わりました。
入居時の修繕積立金は1戸当り月2,500円~3,000円相当で第1回の大規模修繕までに緊急修繕にも費消され、残る資金は1戸当り15.7万円となっていました。
大規模修繕計画資金に必要な不足分を銀行から1億円借入れ、それに先立ち前年には修繕積立金の値上げに踏み切り、総会で居住者の賛意を得た。
第1回大規模修繕では1戸当たり67.4万円
第2回大規模修繕では1戸当たり67.3万円
第3回大規模修繕では1戸あたり77.0万円(この年度の計画修繕工事は除く)
合計211.7万円
第3回大規模修繕は築後30年に当たり、25年から35年にある修繕周期のピークとして捉えられます。このピークを超える準備としてアンケートによる居住者への意識調査「今後20年の建物と暮らしを考える」を実施するとともに、修繕の20年計画を管理会社へ委託作成し、独自の条件を加味して修正版を作りました。
これらが長期計画と修繕計画の根拠となりました。アンケート項目には「修繕積立金の今後20年の見通しについて」もあり、修繕Bの計画項目の実施見通しも付けています。調査報告書はアンケート回答だけでなく、居住者の疑問への回答書が添付され今後の運営に活用されるべきものとなりました。
鉄製の手すりをアルミへ交換せず、補修してリニューアルする決断もアンケート結果が大きく影響しています。
| 項目 | 新築時 | 第1回大規模修繕 | 第2回大規模修繕 | 第3回大規模修繕 | 長期計画 5年後見直し |
| 昭和47年 | 築後11年経過 | 築後18年経過 | 築後30年経過 | 築後 31年~47年 |
|
| 屋上防水 | PC版打 継ぎ目地線 防水 |
断熱材厚15敷込み シート防水 |
4年周期のシルバーペイントで メンテナンスする |
防水層取替え 計画 |
|
| 外壁塗装 | リシン吹付け | 吹付けタイル (複層模様) アクリル系 トップコート |
ウレタン系 トップコート |
シリコーン系 トップコート |
未定 |
| 外壁目地防水 | 油性 コーキング |
油性コーキングを 一部残し、 ウレタンコーキング |
第1回と同じ仕様 | 油性・ウレタンコーキングを全面変成 シリコーン材で 打替え |
〃 |
| ベランダ・ バルコニー防水 |
モルタル防水 | ベランダ床;ウレタン厚2Sバルコニー;エポキシ 厚0.55 |
既存上に 第2回と同じ仕様 |
〃 | |
| 鉄部塗装 | 合成樹脂調合塗料 | 塩化ゴム系塗料 | 旧塗膜と錆を 剥離材で除去し ウレタン樹脂塗料 |
〃 | |
| 補修工事 | コンクリート・ 鉄部補修 |
コンクリート・ 鉄部補修 |
コンクリート部分の徹底的補修 | 〃 | |
| 改善工事 | 階段床・ 踊場床モルタル防水を長尺塩ビシートとゴムタイル貼り(階段) |
階段取外し可能手摺 新設 |
サービス・ バルコニーの仕切板・鉄格子の腐食 部分取替え |
〃 | |
| 外壁色 | オフホワイト色 | 赤みのある サンドベージュ |
第1回と同色 | 茶系 | 〃 |
| 発注方式 | 特命随意契約 塗装・防水など 分離発注 |
第1回に同じ | 指名競争入札 請負方式 |
〃 | |
| 監理 | 管理会社へ委託 | 第1回に同じ | 第1回に同じ | 〃 |
| 設備 | 計画修繕工事 | ||
| 給水設備 | VP管(住戸)鋼管と 塩ビライニング鋼管 |
配管修理、受水槽、 高架受水槽のメンテナンス |
平成14年度 埋設給水管調査後修繕計画実施 |
| 排水設備 | VP管 | 配管修繕工事 | 住戸内排水管取替え および公共下水排水へ 移行を計画 |
| 汚水処理設備 | 500人槽 1300人槽 |
配管修繕工事、汚水調整槽新設メンテナンス | 廃棄 |
| EV設備 | 無し | ||
昭和47年入居時は密実に打設された工場生産コンクリートの防水性能を信頼したコンクリート版の継ぎ目のみ防水した線防水でした。第1回大規模修繕までに屋根からの漏水があったヶ所は集中していたようであり、同じヶ所の修理が繰り返されていたと聞いている。
屋上コンクリート版と接する5階居住階天井にはスタイロフォーム厚10㍉が貼付けられていた。しかし、構造体としての屋上コンクリート版は露出のままであり、気温による膨張、収縮から構造体を保護する必要があった。
第1回大修繕では構造体保護のために断熱材厚15㍉を敷き込みシート防水の工法が採用された。4年毎にシルバー塗装メンテナンスを継続し、シート取り換え周期を延ばしている。30年以降に次の取替えがあるが、工法は未定である。
第1回目の時には修繕委員会において、「5階の居住者だけにメリットがあるのではないか」と言う議論もあったが、「構造体は共用財産である」ことでこの議論は決着した。大規模修繕の初回に起きる疑問であろうが、最近では問題にもならないことであろう。
吹付けリシンから、厚みのある複層模様の装吹付けタイルへと意匠的にグレードアップを図ったのが第1回大規模修繕である。1,2,3と回を重ねる毎に模様上に重ねる塗料(トップコート)性能のグレードをあげ、アクリル系→ウレタン系→シリコン系にした。修繕周期を伸ばすことと、褪色などの意匠性に配慮した。
第1回目にはリシンが落ちたところも含めて段差調整に上パターン付けしトップコートをローラーで塗った。 第2回目は水洗いで剥離したところを同パターン付けし、トップコートが塗られたが、第3回目には既存塗膜をどうするかが課題であった。仕様決定に先立ち塗膜引っ張り試験を外部機関に委託し検討した。
大規模修繕の第2回から第3回の周期は12年あった。外壁状態は塗膜表面にヘアクラックが生じ、面によっては白化がすすんでいたが剥離ヶ所はなかった。今回は打検により塗膜の浮きヶ所を徹底的に剥離補修する工法がとられた。結論的には高圧水洗で剥がれた塗膜、打検により剥がした浮き塗膜を第2回と同じく補修した。塗装業者は3回目も1,2回目工事を受注した同じ業者である。4社中僅差で落札した。
第1回目大修繕において、建物の位置・方向によって既存の油性コーキングがまだ柔らかいヶ所は打換えせず、固く弾力性のなくなったヶ所のみウレタンコーキングに打換えた。施工業者の提案でもあり、工事費も抑えられた。第2回目も同様の方法が採用された。
第3回目では総打換えとし変成シリコーン系コーキングとして外壁塗装と合わせて、修繕周期を延ばそうとしている。
工事委託方法は特命直轄方式から第3回目は4社指名入札に変わったが、統括は塗装業者、下請けに入った指名目地防水業者は3回とも同じである。
第1回、2回、3回と塗料性能のグレードアップを図っている。鉄部塗装の周期は一般的に大規模修繕の半分である。その間は毎年の建物調査により補修している。保証期間を過ぎると補修の費用負担が生ずる。
初回、第1回、2回と塗り重ねられた塗膜と、錆ヶ所塗膜を剥離したヶ所との段差と錆発生が目立ち、腐食、欠損に至るヶ所もあった。過去の大規模修繕においても鉄部の部分補修はなされてきたが、第3回目は大規模修繕の起点に戻る修繕と位置づけ、腐食部分の切除と新設、欠損部分の補強をした後、鉄表面の黒皮まで既存塗膜を剥離剤によって除去する工法が採用された。
積立金の項で「鉄製の手すりをアルミへ交換せず、補修してリニューアルする決断もアンケート結果が大きく影響しています」と書いた。結果、鉄部は旧来の塗装のような段差なくなり滑らかである。且つ、鉄の産業廃棄物を出さずに済んだのである。部分補修ができる鉄と言う材料の長所を生かしたと言えよう。
新築時のリシン仕上げ外壁は浴室バランス釜の排気筒下部の汚れ、キッチンフードの油垂れ、窓下の雨水汚れによる古臭さが目立つようになっていた。白っぽい色から落ち着いた「汚れの目立たない色」への変更が決定された。決まるまでは住戸の一面を使い見本塗装をしていたが、最初の棟の色塗りが終わるや反対運動がはじまり、やがて、終わり、色の変更はなかった。
濃い色(アクリルトップコート)になったせいか、給湯バランス釜の排気筒の高温水蒸気で釜上の壁面が白化する現象が起き、ウレタントップコートを部分塗りし、問題は対処された。
第2回大規模修繕では同色、第3回目ではカラープラニングを外部へ委託しカラーイメージ調査1回、4計画案をについて色決めアンケート2回、計3回実施し、経過も修繕計画ニュースで逐一広報した。色決め投票アンケートート回収率は80%をこえ、関心の高さが示された。色は10人10色であるから納得ゆくように手順を大事に進めた。
工事の準備から竣工後まで「計画修繕ニュース」を発行し、工事のお知らせと注意事項の周知に努めるが、ふりかえると、第1回目大規模修繕では、区分所有について繰り返し説明したように記憶している。2人の広報委員が担当した。
第3回においては21ヶ月間で42回ニュースを発行し、キメ細かに居住者へ対応している。また、居住者のご意見投書箱を設け、ニュースで意見を公表し、委員会で検討した結果を回答広報することを繰り返したが、これによって疑問点が解消されていった。修繕委員の一人が専任で担当し、委員会検討後即日コピー配布され速達便のように居住者へ配布された。工程会議を含めた議事録NO1~86とともに修繕を詳細に記録している。修繕委員会は週1回のペースであった。